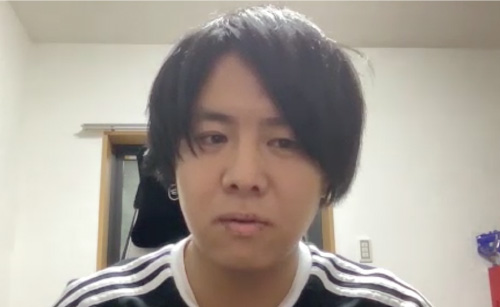Vol.31映画監督・マルティカ・ラミレス・エスコバル × 映画監督・木村聡志
「パッションを形にするためだけに映画を作る」(マルティカ)
「自分の映画を観た後に 幸せを感じてもらえたら」(木村)
木村監督からマルティカ監督に聞いてみたいことは?
木村「『レオノール』は多層構造になっていて、劇中劇があり、その劇中劇の撮影が終わっても、今度は現実世界の話が続くというシーンがあったりします。ああいうシーンでは俳優さんたちにどう演出をするんですか?」
マルティカ「ああいったシーンの多くは即興です。俳優さんを起用するお金がなかったので、私自身が出演したり、私の家族や友人たちにも出演してもらっていて。即興を多く取り入れている事情のひとつには、そういう、プロの俳優ではない人たちがたくさん出演しているからというのがあります。あと、もともと自分の中では世界はひとつではないと思っているところがあって。それで、どこからフィクションで、どこからアクションで、どこからドキュメンタリーなのか、その世界の線引きをあえてしないようにと思っていました。即興と言えば、エリック・ロメールの映画は即興芝居が多いと言われますが、『違う惑星の変な恋人』では即興もあったんですか?」
木村「基本的に即興はないです。言い間違えた、みたいなところも、あらかじめ脚本にそういうふうに書いてあります」
マルティカ「撮影中に台詞を書き換えたりはしないですか?」
木村「基本的に書き換えないです」
マルティカ「それは脚本が本当によくできているということですね」
木村「ありがとうございます。脚本と言えば、僕の脚本はほとんど台詞だけで埋められ、ト書きはほぼありません。『レオノール』の劇中劇の脚本には登場人物の動きや感情も含め、詳細なト書きが書かれていましたよね。普段からそんなふうに書いているんですか?」
マルティカ「私はカメラマンとしても活動していて、どうしても最初にイメージが思い浮かびます。だから私はト書きから入るんです。台詞が思い浮かぶのは最後で、もっと言うと撮影時にプロデューサーたちに相談しながら書き換えていくこともよくあります。木村さんの台詞から入るアプローチは私とは正反対で面白いと思いました。撮影に関してはカメラマンとどう話して、どうショットを決めていくんでしょうか?」
木村「撮影前に2回ほどオールスタッフでロケハンをして、演出部のスタッフに俳優の代役をしてもらい、“なんとなくこう動くかも”と想定します。それを見ながらカメラマンさんとどう撮るか、照明はどう作るかなどと相談して。で、撮影の時には俳優さんたちと対話しながら、まずこちらから“最初にここに座って”などと提案してみます。でも俳優さんが“最初は座っていないほうがいい”と言ったら、その場で撮影プランを全部変えます。キャラクターを一番理解しているのは演じる俳優だと思っているので」
異なる作家性を持つおふたりですが、オリジナル企画・脚本で勝負されているという共通点があります。
マルティカ「私は映画を作るにあたって自らに質問を投げかけます。なんのために、誰のために、なぜ作るのか、という質問です。私は普段、お金のためにテレビCMなども撮っています。一方の映画はなんのために作るかというと、自分のパッションを形にするためなんです。『レオノール』を作る時も、予算が少なく、たくさん犠牲にすることはあると最初からわかっていたけれど、どうしても私と友人のパッションを映画という形にしたかった。で、それはやっぱり商業的な映画ではできないんですね。本当に自分たちの作りたい映画はオリジナルでしかできないものだった。オリジナル映画は作るのが難しいものですが、一方で何か新しいことができる。トライする価値があるものだと思っています」
木村「今の日本では、映画ファンではない一般の人たちがオリジナルの映画を観る機会はほとんどないと思います。それでもオリジナルで作り続けるのは、第一に自分が映画が好きだから。そして、オリジナル映画を観た後だけに感じられる幸せがあると思うからです。そういう幸せを自分の映画を観た後に誰かに感じてもらえたら素晴らしいと思っていて。あと、オリジナルは確かに作るのが難しいですが、同時に“自分はこういうことができます”と、わかりやすく伝えられるものだとも思うんです。今までなんとか続けてきて、できないことはないと実感しています。これからもオリジナル企画で映画を作り続けたいと思っています」